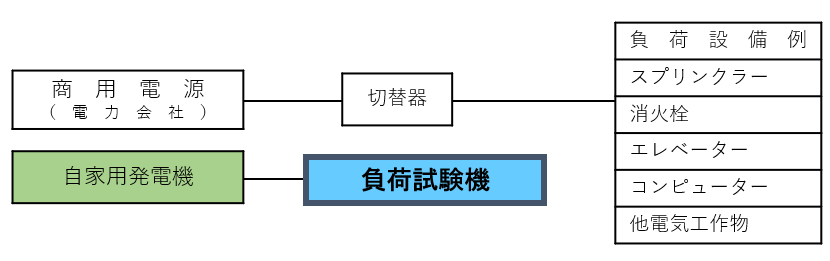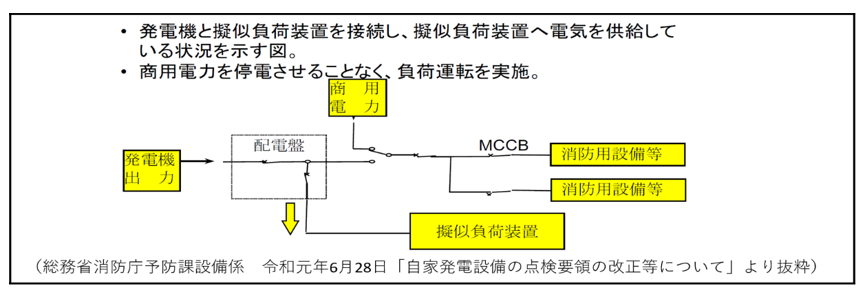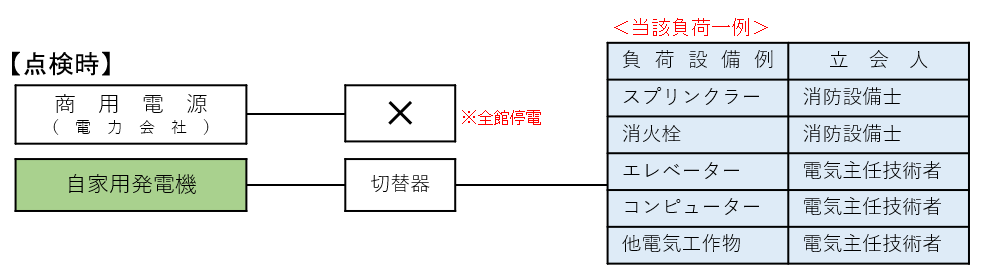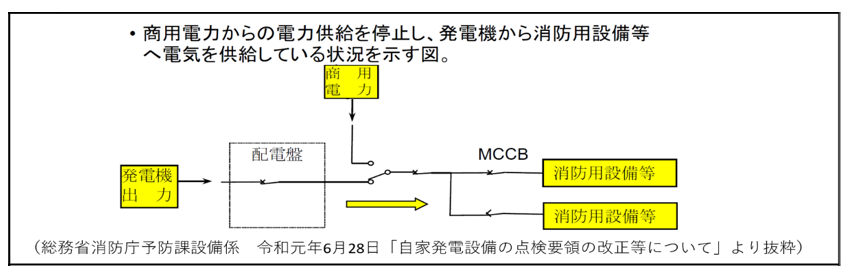負荷試験装置による30%負荷試験作業
(試験機の搬入搬出時間も含め、無停電で約1時間30分の作業)









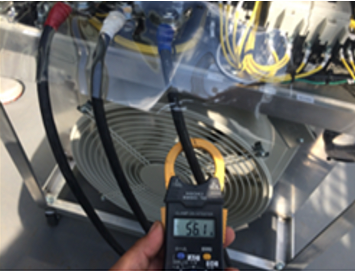



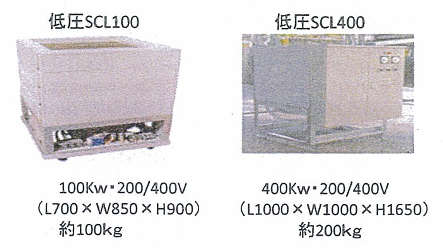
|

|






|
非常用発電機
第3節 自家発電設備 (総務省消防庁・消防予第214号 第24-3総合点検の39頁目 負荷運転より抜粋) |
|
非常電源を必要とする消防用設備
|
非常電源専用受電設備
|
自家発電設備
|
蓄電池設備
|
容量
|
根拠条文
|
|
屋内消火栓設備
|
〇(注)
|
〇
|
〇
|
30分
|
消防法施工規則第12条第4号
|
|
スプリンクラー設備
|
〇(注)
|
〇
|
〇
|
30分
|
消防法施行規則第14条第1項第6号の2
|
|
水噴霧消火設備
|
〇(注)
|
〇
|
〇
|
30分
|
消防法施工規則第16条第3項第2号
|